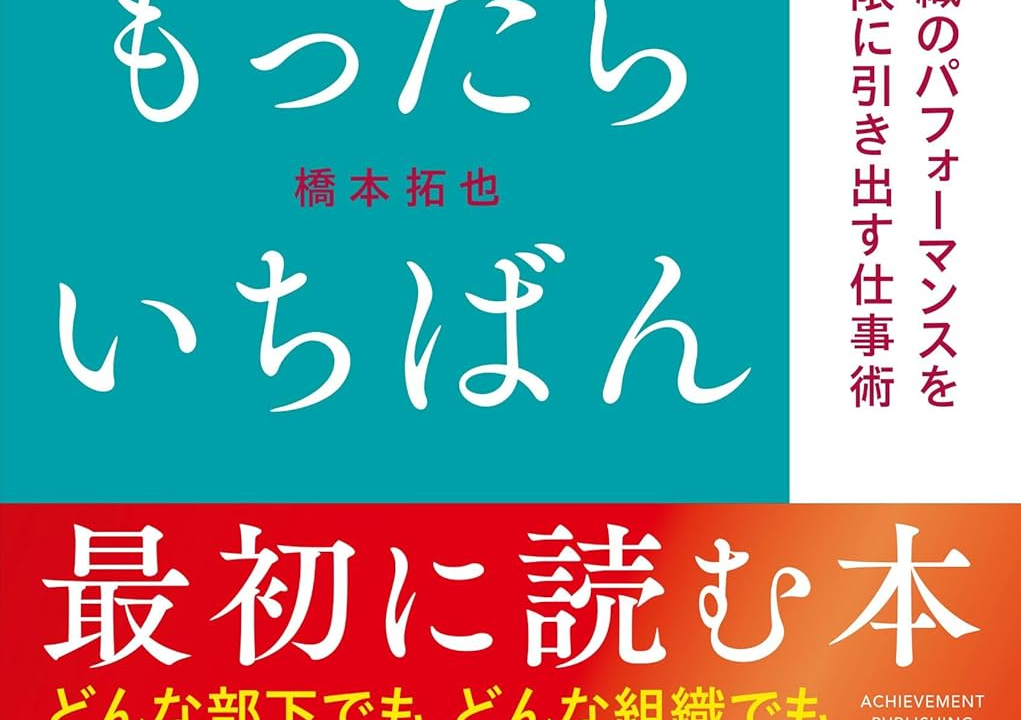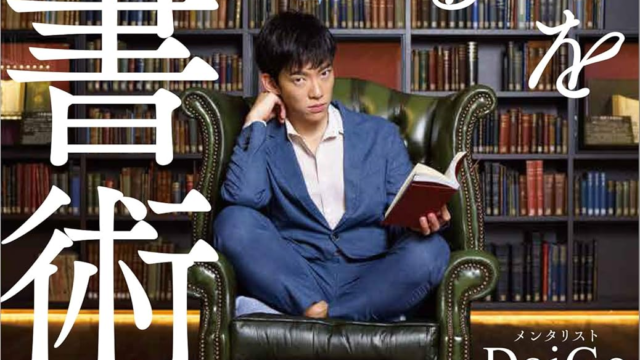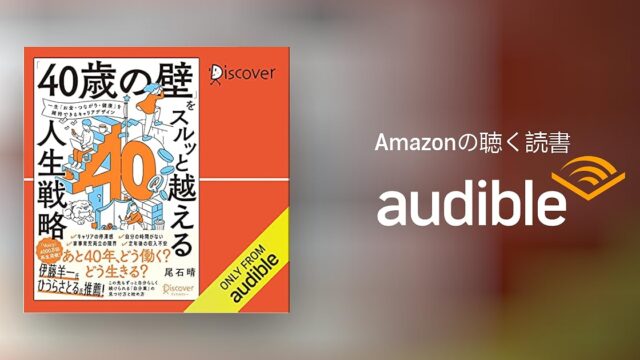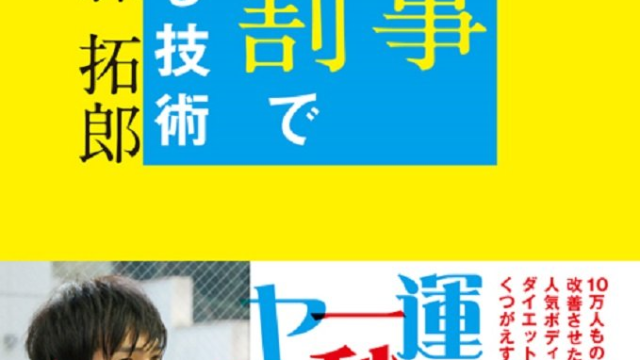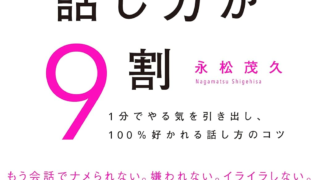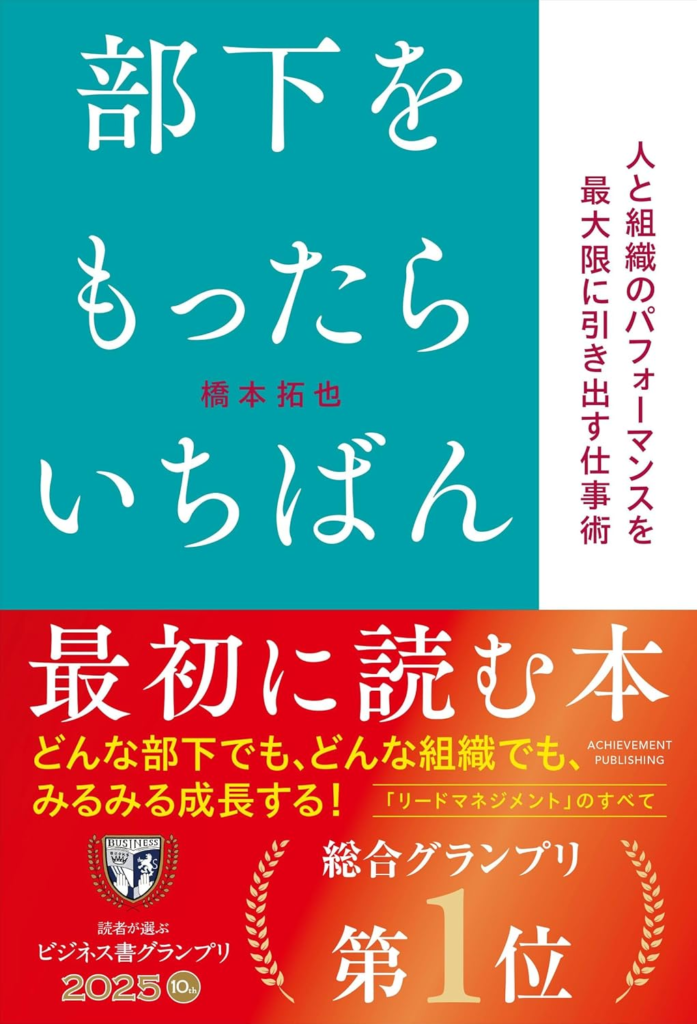
※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
あなたは自分のマネジメントに自信がありますか?と聞かれてあります!と答えることができる猛者は果たしてどれくらいいるのでしょうか。
僕は今までまともな会社では働いたことがなかったのですが、転職してある業務内でのリーダーを務めることになりましてとても難しさを感じています。
そんなときに「部下をもったらいちばん最初に読む本」とうタイトルに惹かれて読んでみました。
「マネジメントは技術。学べば誰もが習得できるもの」と書かれていてマネジメントが苦手な人を優秀なマネージャーに導いてくれる本です。
あなたのマネジメントがうまくいかないのは、無免許運転をしているせい――。
部下をもってマネジメントを任されるようになり、プレイヤーからマネジャーになり、その仕事の変化に悩む人たちの声をよく耳にしますが、本書がその解決策として提案するのは、「マネジメントは技術。学べば誰もが習得できるもの」ということ。
そのノウハウ「リードマネジメントのすべて」が詰まった本書は、2万人の研修実績を誇るトップコンサルタントである著者がたどり着いた、心理学をベースにした新しいマネジメントの手法をまとめた一冊。
全マネジャーの必読書が登場です。
~Amazonより~
このブログでもこの本のポイントをご紹介させていただきます。
気になった方はオーディブルの聞き放題対象作品にもなっていて、キャンペーンで全編無料で聞けたりしますのでぜひお試しください。
↓
このブログでは特に印象に残った項目を紹介していくね!
目次
間違ったマネジメントについて
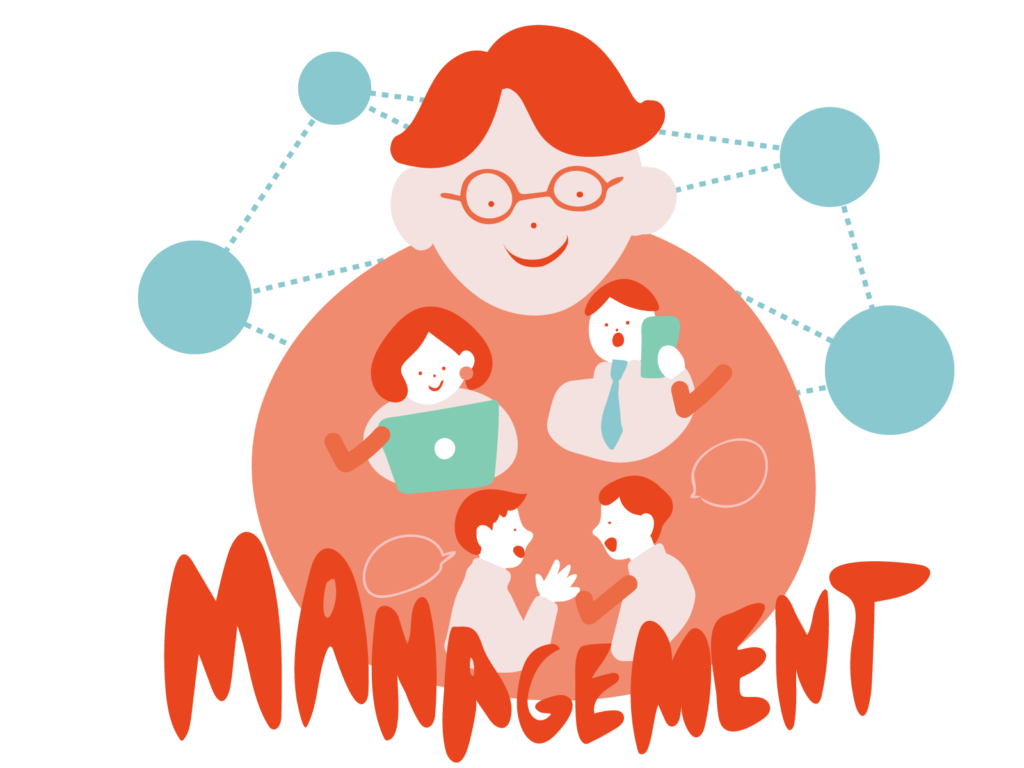
よくある間違ったマネジメントで、上司が部下に対して外側からの刺激によってマネジメントをしていこうというものです。
例えば信賞必罰といった、よくやったものには褒美を与えてノルマを達成しないものには怒鳴りつけるといった外側から刺激によって人を変えようとするのは人の行動のメカニズムから外れています。
本書であげられている間違ったマネジメントの仕方を3つご紹介します。
ボスマネジメント
部下を怒鳴りつけたりガミガミ言って、自分の思い通りに動かそうとします。
放任マネジメント
君の好きにやるといいよ。と言ってマネジメント自体の放棄をします。優秀な部下がいると組織が上手く回る場合もありますがマネージャーがいる意味はありません。
言いたいことが言えないマネジメント
自分の腕に自信がないマネージャーが陥りがちで厳しく言うべきときに言えなかったり、部下の成長をサポートできません。ごめんね、こんな上司で。と卑下するようなことを言って「そんなことありませんよ」と相手にフォローの言葉を言わせようとします。
ではどうしたらいいのか?本書から一部抜粋してお伝えします。
目的、目標を明確にする
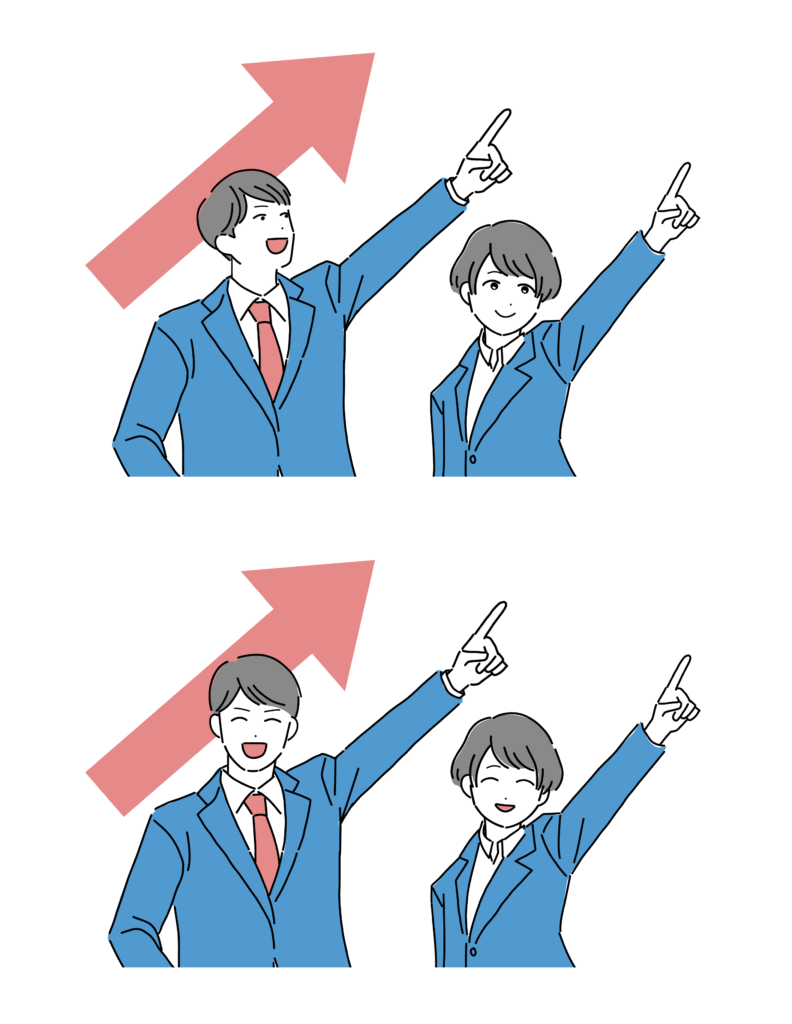
目的と目標を明確にして部下を導いていくことが大切なのですが、目的と目標の違いは何でしょうか?
目的:なんのためには?誰のために?なぜあなたがこれをやるのか?という仕事の動機
目標:〇月までに営業数字を〇%アップなどの目に見えるもので達成を目指す。
問題なのは、目標だけでは動けない人もいる。という点です。
目的と目標をわかりやすくとらえるために有名な「3人の石工」という逸話をご紹介します。
石工とは建物を建てるためのレンガ職人のことです。
ある3人の石工にあなたは何をしているのか?を聞きました。
1人目:この仕事で生計を立てているのさ。
2人目:この国で1番上手な石切りの仕事をしているのさ。
(手を休めずに働いている)3人目:未来の大聖堂を作っているのさ。
(目をキラキラさせながら働いている)
この3人の石工には共通してレンガを積み上げて建物を建築するという同じ目標が与えられています。
目的の持ち方によって働き方のモチベーションが段違いになります。
1人目と2人目の石工の働く目的もそれぞれの人によって立派な目的なのですが、極論この組織でなくてもできることです。
優秀なマネージャーが目指すのはこの組織の一員だからこそ成し遂げられる達成感、仕事の目的に導いてあげること。
この逸話の3人目の石工のように組織の中で、主体的に自分が働く意義をしっかり感じてモチベーションの高いメンバーに導くことです。
ギャップフィードバックを成功させる3つの視点

メンバーの育成を促すためには褒めることも大切ですが、出来ていない部分について成長を促すようにフィードバックを伝えなければなりません。
できていないギャップを埋めるためのギャップフィードバックをうまく使いこなして優秀なマネージャーを目指したいですが、耳の痛いことを伝えるのは気が引ける方も多いですよね。
そこで、ギャップフィードバックを成功させる3つの視点をご紹介します。
1、誰が言うか
まず第一に誰がそのフィードバックを言うかということも大切です。
例えば極端ですが、上司が毎日遅刻してしまっている人だとしましょう。
その毎日遅刻上司から、「遅刻しないように」と言われても全く説得力がないですよね。
このようにまずは上司側がフィードバックする内容を模範として示せているかということは大切なので日ごろの行いから気を付けていきましょう。
2、何を言うか
伝えるべき内容は、現状の把握。問題点のすり合わせ。改善計画の立案の3つあります。
現状の把握では状況、行動、発言、周囲への影響などを事実に沿って伝えます。
問題点のすり合わせでは、問題の焦点を人ではなく事(こと)に合わせていく。
問題を起こした犯人捜しをするのではなく、この問題が起きてしまった仕組みに焦点をあわせていきます。
改善計画の立案では、同じ問題が起きないように次はどうするかを話し合います。
もしも時間を巻き戻すことができたら問題が発生しないためにはどうしたらよかったかを話し合ってもらいます。
3、どのように言うか
基本的に言うべきことを明確に伝えるというスタンスです。
伝えるときに気を付けたいのが私は。と自分を主語にして伝えること。
例えば、遅刻してきた部下に「あなたが遅刻してきたのでみんなが迷惑している」というのではなく「私は、あなたが遅刻してきて残念に思っている」
という風に自分がどう感じているのかという伝え方にすると相手から否定されないようになります。
もうひとつは大前提ですが、感情的にならないことです。
感情的になると相手からも怒りをぶつけられたという感情しか受け取ってもらえなくなるのでメンバーとの関係性が悪くなるだけで肝心な成長につながりません。
組織の水質管理もマネージャーの役目
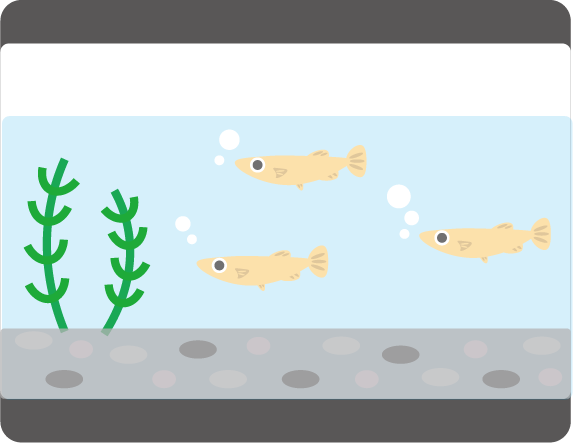
組織はよく水槽にたとえられます。水が汚れた水槽では魚の元気がなくなりますよね。
組織をいい水質の水槽にして中にいるメンバーにイキイキ働いてもらうのもマネージャーの役割です。
そんなの難しそうだなと感じてしまうかもしれませんが、本書では2つのヒントを出しています。
1、1人1人のメンバーを強くする
まずは、組織にいるメンバーの1人1人をしっかりと強く育成することが大切です。
やはり一番大切なのは、目的と目標を常に明確に伝えること。その仕事をなぜ行うのか?
マネージャー自身が理解してメンバーにあなたがこの仕事をやる理由。をしっかりと伝えること。
仕事を一緒に進めていく中でメンバーに対してポジティブフィードバックはもちろん、言うべき時は正しい伝え方でギャップフィードバックを行いマネージャーが導いてあげることが大切です。
そうして目標、目的がしっかりとしたメンバーが増えてくれば組織の水質も自然と良くなってきます。
2.組織全体で同じ方向を向いて進む
メンバーを育成すると水質がメンバーによってだんだんよくなってきますが、水槽の水をきれいに入れ替える作業も同時に行いましょう。
チームの一体感を出すためには、①共通目的。②共同意欲。③コミュニケーション。
が必要不可欠です。
①共通目的は誰のために?何のために?なぜ私たちの組織が存在しているのか?を明確にして認識すること。
②共同意欲は互いに協力しあいながら、物事を成し遂げようとする意識のこと。
③コミュニケーションはトップ一人がいつも発信するのではなくメンバー間でも情報の発信ややり取りがある状態を指します。
この3つが整うと組織の水質がどんどんよくなっていきます。
最も影響力を持つのは上の立場にいる人の発言や行動なので、経営者やマネージャーが率先して企業理念を大切にした発言や行動を日ごろから心がけましょう。
ふさわしい企業理念がないと考える場合には、①の共通目的はマネージャーが自ら作成して組織に根付かせていきましょう。
感想、まとめ
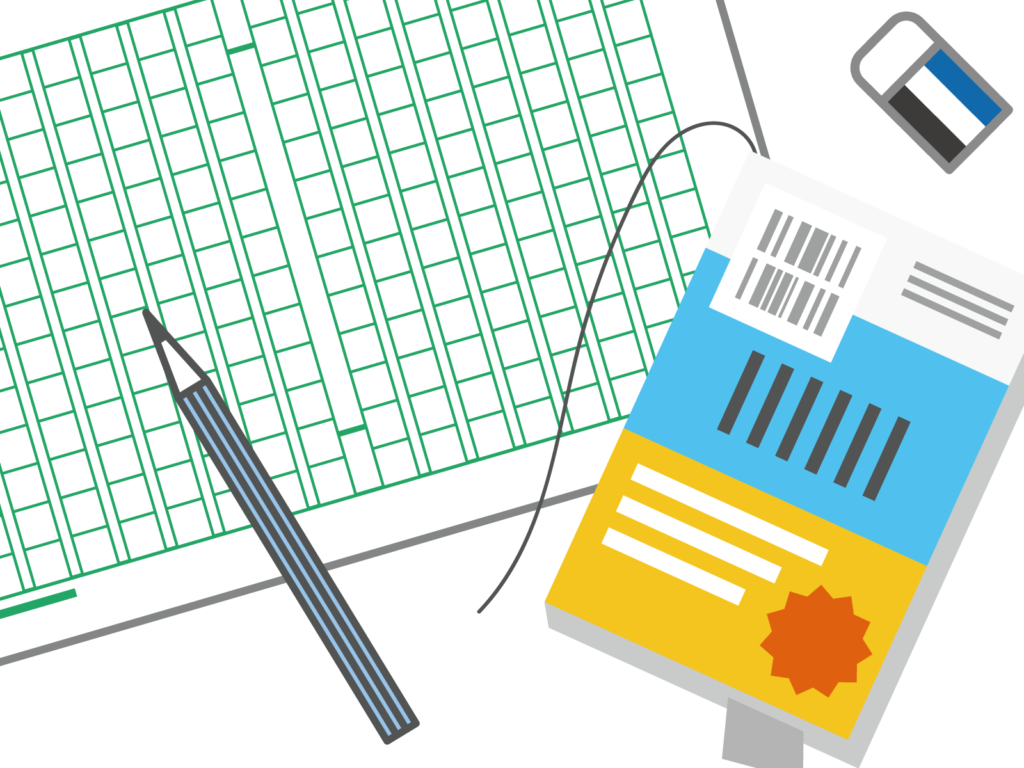
この本を読もうと思ったのは僕自身がマネジメント経験が今まではなく、ある業務でメンバーを統括する立場になり難しさを実感したからです。
自分の仕事のおろし方がまだ不慣れなためにメンバーたちも仕事の奥行について考えることができなかったり、いまいち成長にはつながっていない実感がありました。
僕が特に大切だなと感じた部分は目的、目標を明確に伝えることが大切という部分で、
なぜやるのか?ということを理解できていなかったのは自分自身だということに気づいたんです。
それから下手なりにも、なぜやるのか?あなたがこの仕事をやる理由など、背景までつたえることを意識したところメンバーの意識も徐々に変わってきており、自分の上長からも少しずついいマネジメントができていると評価をいただくことができました。
リードマネジメントを実行するとメンバーが主体的に働いて成長していけるようになります。
この本で紹介されているリードマネジメントの技術は5つあり、リーダーシップの技術。個人の成長支援の技術。水質管理の技術。委任する技術。仕組化する技術の5つです。
この記事では紹介しきれなかった技術や具体的な手法の解説などがたっぷり盛り込まれておりますので気になった方はぜひ一度読んでみてください。
お試し期間を使って無料で本を読もう!
本を実質無料で読みたいという方は下記のリンクから無料期間中のうちに本を読み終わってプラン解約すると実質無料で読むことができます。
(たまにキャンペーン企画の変更が入りますので詳しくはリンク先でご確認いただきたいです)
↓
オーディブルを無料で試す無料期間中にも簡単にやめることができますので、他に気になる本がなかったりしたら本書だけ読んで無料期間中にやめると0円です。
(たまにキャンペーン企画の変更が入りますので詳しくはリンク先でご確認いただきたいです)
ちなみに僕はオーディブルを継続活用していて月会費を払っていますがすごいコスパのサービスだと思っています。
今でも続けて色んな本を通勤時などに聴いていますので移動時間も楽しいです。
なのでまたこれはいい本だ!と思う本を見つけて当ブログでご紹介させていただきますのでよろしければブックマークなどしていただけると大変嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またねー!!